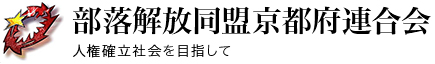新着情報
2024.08.29
「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会」とりまとめ(案)のパブリックコメント提出について
部落解放同盟京都府連合会(以下、京都府連)は2024年8月9日、総務省の有識者会議がまとめた対策案で募集されていたパブリックコメントに意見を提出しました。
この対策案は「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会 とりまとめ(案)」で、ネット上の偽・誤情報への対処で方針を示したものです。京都府連からは主に3つの観点から意見を出しました。
偽・誤情報を「有害性のある情報」と定義していたところ、ここに差別情報も盛り込むべきと主張しました。各関係機関(マルチステークスホルダー)で組織する協議会が必要との提言もあった。情報交換をするとき、偽・誤情報で被害を受けた当事者の意見を採り入れるよう指摘しました。
発信者への対策や広告主の経営層などへの働きかけの必要性なども提示しました。詳細は、下記のとおりです。
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
部落解放同盟京都府連合会からの意見
- マルチステークスホルダーとの協議会では当事者の意見を採り入れるべき
削除の必要な偽・誤情報の中に、法務省人権擁護局による「インターネット上の人権侵害情報による人権侵犯事件に関する処理要領について(通知)」の類型にある「不当の差別的言動」や「識別情報の摘示」といった属性を理由とした差別情報を含めるなどし、個人や組織、国家以外にも有害性のある情報への対処も必要だ。差別情報を詳しく調べると、「差別をしていないと装って発信される悪質な情報」「誤った情報を鵜呑みにしての義憤による攻撃的な投稿」などもあり、見極めて削除する必要性が出てくる。これができないとPF事業者が対処にあたる際の実効性の担保は難しい。当検討会は、マルチステークスホルダーとの協議会でケースごとに利益代表となる主体の参加を判断し、情報交換の場の設定する方向性を示した。削除の働きかけや被害者のケアをおこなってきた当事者支援団体や地方自治体などの意見を取り入れる重要性は明確にある。健全な情報空間構築には当事者を抜きにしない対策が不可欠で、対話によって属性等の違いを乗り越えようとする取り組みは、憲法十二条にある「国民の不断の努力」そのものだ。実効性担保のためにも、対話による解決が積極的にできるよう、連携・協力体制の制度整備の必要性を強く示されたい。
- 発信者へのアプローチが必要
発信者の中には、繰り返し悪質な差別情報を投稿し続ける者もいる。この者らへ直接の働きかけが偽・誤情報をなくすための本質的な対策となる。PF事業者はアクセス情報など把握できる立場で、事業者間での情報共有ができれば、「産」による面的な対策を講じることもできる。「官」が旗振り役となって発信者へのアプローチを可能とし、「民」や「学」も交えて、対話の中で発信者が差別と向きあい、許されない行為であることを自覚し、二度と繰り返さないと決意するまでの意見交換等を実施できるような取り組みも考えるべきだ。民産学官の共働で解決に導く先進的な取り組みを考案されたい。
- 広告主の経営層レベルでの差別を許さない意識を醸成すべき
別紙の「第6章」に関しては、広告主の経営層レベルでの判断を後押しする必要性も示されたが、そもそも差別を放置するPF事業者に広告を出している広告主には、この認識も問わねばならない状況でもある。差別情報の投稿は表現の自由の濫用だ。表現の自由を理由にした差別の放置は無責任で、こうした対応を続けるPF事業者は決して許されない。行政や企業も広告主となっている。これらが人権感覚を欠き、主体性の欠落した状態で、差別投稿に何の意見も言わないようでは、PF事業者による差別の放置に加担していることにつながっている。ネットに関わる主体のすべてが社会的責任を自覚して取り組みをすすめるべきだ。これまでの在り方を大きく転換できるような踏み込んだ提言をされたい。
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/